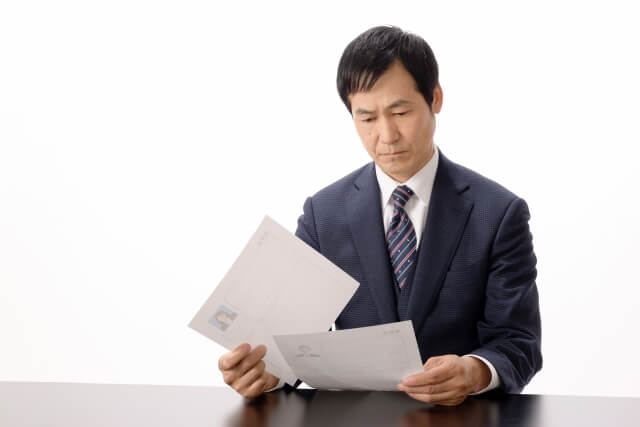最終面接で落ちるとさすがにショックでなかなか立ち直れません。何がダメだったのか、理由を知りたくても採用担当者は教えてくれません。
一次、二次面接と最終面接の違いは役員が出席するため、雰囲気がガラッと変わることです。実は雰囲気だけでなく、合格基準が大きく異なるのです。
私は大手企業の新卒採用活動を15年以上している現役面接官の「はれきち」です。役員がどのようなタイプを好むか、あるいは嫌がるか私は熟知しています。
- 最終面接は決裁者が人事部ではなく役員になる
- 一次、二次は能力重視、最終面接は熱意重視になる
- 入社意欲の高さは企業研究の量に比例する
- 最終面接は最初の5分が勝負
この記事を読むと最終面接では社長や役員が出席するため、理論的な回答より熱のこもった回答を好むことがわかります。入社意欲の高さは同業他社分析などの企業研究の量に比例するため、しっかり対策を練ってのぞみましょう。
役員には入社熱意が一番のアピールになる
~文系就活生が登録すべきおすすめ就活サイト3選~
・最短2週間で内定ゲットできる
・対面だけでなく、TELやWEBで対応可能
・Googleの口コミが4.7の高評価
・就活に出遅れたと思ってるなら必須
・逆求人サイトなら絶対登録すべき神サイト
・登録企業19,807社からのオファーは内定への近道
最終面接で落ちる理由

最終面接までいけば、内定をもらったも同然と考えてはいけません。最終面接は2人に1人が落ちています(私の会社で実証済み)。
ではどんな理由で落ちるのでしょうか?
私はこれまで最終面接で何百人と判定してきました。不合格になる理由はこちらです。
<落ちる理由>
- 入社意欲が感じられない
- 元気(覇気)がない
- ほとんど主張がみられない
- 独自のカラーがない
- 保守的な発言が多い
- こだわりが強すぎる
- 志望動機がブレている
- 志望順位が低い
- 同業他社分析をほとんどしていない
- 質問の意図を理解していない
- やりたいことが業務内容と不一致
- 回答を暗記に頼りすぎ応用がきかない
- 勤務地にこだわりすぎる
- 回答がほとんど抽象的すぎる
- ほんとは他社を志望している
これらが役員や採用担当者へ伝わると落ちてしまうのです。何しろ最終面接の面接官は百戦錬磨の猛者(もさ)達ですから。
第一印象でどんなタイプかすぐ見抜いてしまいます。よって、雰囲気が暗い、目を合わせない、声が小さいのは問題外となります。
でもそんなにビビる必要はありません。一次、二次面接をクリアしているので、誰に内定を出してもよいレベルに達しているのです。
ただ、最終面接に進んだにもかかわらず、もう一歩届かないのには原因があるのです。特に多いのは次の3つです。
<主な原因>
・熱意を感じられない
・志望動機がブレる
・こだわりが強すぎる
熱意が感じられない
一番は『入社意欲を感じられない』ということです。
・早く仕事を覚えたい
・バリバリ働きたい
・顧客のためにもっとよいものを作りたい
・世の中にもっとよいサービスを広げたい
わかりやすくいうと、「自分を入社させると得ですよ!」と訴えかける力が弱いのです。気持ちが表に出ないと何を考えているか、わからないのです。無表情で回答したり、淡々とした一本調子で話すと、とても熱意があると感じられません。
私は一次、二次面接で能力が高い人材と判断し合格を出したのですが、最終面接で役員の印象が悪く、不合格となった人を山ほど見てきました。
 はれきち
はれきち入社したいアピールをもっと出さないとね
志望動機がブレる
一次面接に伝えた志望動機、二次面接で深掘りされた志望動機、最終面接で確認された志望動機がブレていると落ちます。
志望動機は入社する根幹なので、毎回変わると印象が悪くなります。
「就職したい根拠が不明確」と判断されるのです。
例えば、最初の志望動機が「人と接することが好きなので営業をやりたい」と言っていたのに、途中からやっぱり技術職に興味を持ち、最終面接では「どちらでもOK」となった場合です。
志望動機が途中で変われば、面接官を納得させる理由が必要になります。面接官は結局、どちらの職種をやりたいのかわからないのです。
その他、就活状況が食品業界に関心があるにも関わらず、IT業界や家電業界の就活をしていたら「一体何がしたいのだろう」と疑問を持たれます。
このような考え方だと、「内定が取れれば何でもいいの?」と判断されます。
こだわりが強すぎる


こだわりや主張が強すぎると敬遠されます。
【こだわりと主張】は一見、聞こえがよいですが、【頑固、柔軟性がない】と受け取られれば落とされるのです。
勤務地を実家から通える範囲にこだわったり、採用者から営業向きと言われたのに、研究職以外考えられないと主張すると適応範囲がかなり狭い人と判断されます。
採用者は選択の余地が少ない人より、幅広く融通が利く方を選んでしまうのです。
主張しないのもダメですが、強いこだわりは逆に敬遠されるので注意しましょう。強いこだわりは柔軟性に疑問を持たれ、部下として扱いにくいと判断されます。
非常に優秀だと判断しても顧客や上司とかみ合わないタイプは不合格となります。
結局、最終的に選ばれるには相手に【一緒に仕事がしたい】と思わせるかどうかなのです。
最終面接は一次、二次と合格基準が違う


最終面接は一次、二次面接と雰囲気が大きく違います。実は雰囲気だけでなく、合格基準も違うのです。
その理由は、最終面接は役員(社長もしくは取締役)が出席するためです。就活生だけでなく、われわれ人事部も緊張感はありますが…。
| 最終面接 | 一次・二次面接 | |
| 決裁者 | 役員(取締役) | 人事部 |
| 能力 | 熱意重視 | 能力重視 |
| 評価 | 相対的 | 絶対的 |
決裁者が人事部から役員へ
一次、二次面接の合否を決めるのは人事部です。しかし、最終面接だけは役員が最終的に合否を決めるのです。
最終面接は人事部だけでなく、社長や取締役が出席します。
例えば、社長が『合格でよい』と言っているのに、人事部が『それはダメですよ』と強く否定することはできません。
人事部が『不合格』と判断しても社長が『合格でよい』といえば、合格になるのです。そうなんです、決裁権が人事部から役員(社長や取締役)へ移っているのです。
よって、役員の最終判断が合否と直結しているのです。
一次、二次面接までは人事部目線ですが、最終面接は役員目線が重要になります。
役員と人事部では見ているポイントが大きく違います。これまで人事部に評価された点が役員に通用するとは限りません。
逆質問も一次、二次と最終面接でうまく使い分けた方がよいのです。
>>【実証済み】一次、二次、最終面接の逆質問で落とされる【ワードとNG集】
能力重視から熱意重視へ
一次、二次面接では能力重視ですが、最終面接は熱意重視となります。
わかりやすく言うと人事部は能力重視、役員は熱意重視で合否を判断しています。
| 人事部が評価する能力 | 役員が評価する熱意 |
|---|---|
| ・コミュニケーション力 ・適応性 ・危機対応 ・チームワーク ・リーダーシップ | ・入社意欲 ・忠誠心 ・チャレンジ精神 ・ポジティブな考え ・行動力 |
当然、会社は『能力が高く』、『やる気』のある人に入社してほしいのです。
この『能力が高く』の部分が一次、二次面接で重視され、『やる気』の部分を最終面接で重視しているのです。
一次、二次面接は能力重視
一次、二次面接の合否の判断材料はズバリ【能力】です。
人事部の採用担当者はコミュニケーションがしっかり取れるか、仕事に適応できるか、逆境に耐えれるか、チームワーク、リーダーシップの能力があるかないかで合否の判断をしています。
企業が求めている基準に達しているかどうかで判断しています。
グループディスカッションや集団面接を通して、面白い考えや独特な発想、奇抜な回答しても「この人は能力が高い」と判断すれば、合格となるのです。
最終面接は熱意重視
能力を重視する人事部と異なり、最終面接の役員は熱意を重視しています。役員は「やる気」という言葉が大好きで、気持ちを最優先に考えています。
なぜなら、一次、二次面接を通して、能力の高い人がすでに厳選されているためです。
入社意欲が高いと最も評価されます。そのため、志望順位の低さや他社志望に気持ちが傾いていると見透かされると落とされます。役員の質問は巧みに誘導するテクニックを使うので、つい引っかかってしまうのです。
「是非、御社で働きたい!」という気持ちだけでなく、表情に表すとより役員から好まれます。
絶対から相対的評価に
一次、二次面接は絶対的評価になります。よって、会社が求めている能力があると判断すれば、合格となります。しかし、最終面接においては、採用数が決まっているので、相対的評価になります。
例えば、採用数が10人であれば、最終面接をして、入社してもらいたい人が12人いたとするとそこから相対的評価で2人落とさないといけません。
よって、何が悪いから落ちるのではなく、相対的評価で落ちる場合があるのです。
採用数の人員は計画で決まっており、予算にも反映されます。そのため勝手に採用数を増やしたり、減らすことはできないのです。
最終面接の合格率
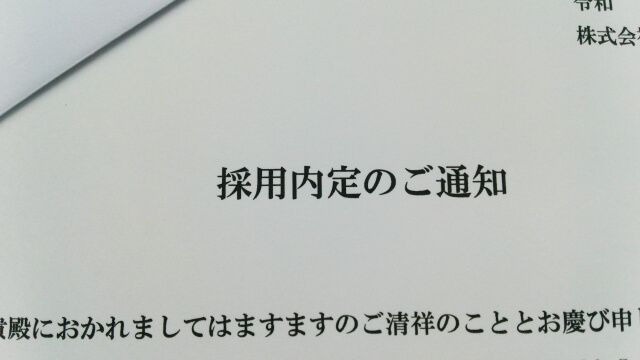
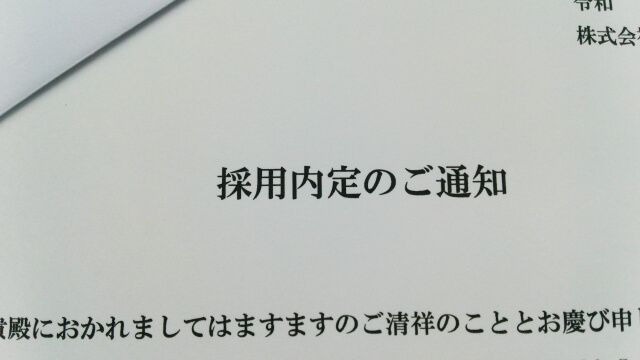
最終面接は2人に1人が落ちると言ったのですが、それには根拠があります。私の会社でここ5年の最終面接の合格率をはじき出した結果はなんと『53%』でした。
ネットで言われている確率は50%なので、あながち間違いではないです。ただし、私の会社では年により40%台があれば、50%後半もあるため、ブレ幅はかなりありました。
厳密に言えば、営業職、技術職、研究職によっても異なるし、配属が東京、都市、地方によっても大きく変わるのです。
詳しく知りたい方はこちらを参照ください。
>>【合格率53%】最終面接の確率は希望職種や勤務地で変わる【新卒必見!】


自分は最終面接で勝負できるレベルに達しているか、面接力診断で調べることができます。
80点以上であれば、全く問題ありませんが、59点以下だともう一度面接対策を練り直す必要があります。
チェックしたい人は➡面接力診断
役員が評価する熱意とは


人事部が接するのは一次、二次、最終面接を含め合計3回となります。三次があれば、4回となります。
しかし、役員の出席は最終面接の1回だけとなります。そのため、細かい部分は人事部がまとめたレポート(一次二次の評価)で確認する程度となります。
役員の考えでは最終面接に残るということは能力的にはクリアしていると判断しています。(能力が低い人が最終面接で多いとあとで人事部が怒られるますから)
よって、判断材料は入社意欲などの熱意に重点がおかれます。役員の判断でもっとも重要視するのが、『入社意欲』と『忠誠心』です。
他社への浮気心が少しでもあると巧みな誘導質問によってバレてしまいます。
<役員が評価する熱意>
・入社意欲
・忠誠心
・チャレンジ精神
・ポジティブな考え
・行動力
入社意欲
入社意欲が高いか低いかで印象は変わります。例えば、入社する確率を聞かれ、『70~80%です』と答えると役員の印象はかなり悪くなります。
逆に入社意欲が高い発言をすると印象がよくなります。役員はまず入社意欲が低いと合格は出しません。



入社する可能性を100%と答えると評価高い
忠誠心
忠誠心と書いて引かないでくださいね。要は業務内容の仕事が好き、志望会社が好きかということです。
役員は純粋に入社したらできるだけ長く働いてもらいたいのです。
そのため好きな仕事なのか、本当にやりたい仕事なのか確認されます。まさに『好きこそ物の上手なれ』なのです。役員は入社歴が長い人が多く、愛社精神が強いのです。
チャレンジ精神
役員は会社というフィールドを使って、新しいものに挑戦してもらいたいという気持ちがあります。よって学生でまだ若いのに保守的な考えの発言が多いと落胆します。
ワークライフバランスや働き方改革と企業は取り組んでますが、休日出勤や残業したくない気持ちが伝わると嫌がられます。
一員となったからには何かを絶対やり遂げる気持ちが大事になります。
そのため、苦手なことや困難を克服したり、やり抜くアピールが大切です。
ポジティブな考え


役員は暗いより明るい人、愛想が悪いよりよい人、後ろ向きより前向きな発言、悲観的より楽観的、消極的より積極的な考えを好みます。
あまり深読みはせず、シンプルに物事を考えた方がよい結果につながります。
口角を上げ、少し前のめりぐらいの姿勢で丁度よいです。性格的にネガティブでもここだけはムリをして、ポジティブスイッチを入れましょう。
自信がなくても、目線をそらさず、まっすぐ見て話をすれば、それらしく聞こえますから。前向きな考えがないと次から次へとあらわれる壁を乗り越えられません。
行動力
熱意が伝われば、しっかり実行できる人材なのか最後に見極められます。
知識が豊富、頭の回転が速く能力が高くても頭でっかちと判断されれば落とされます。そのため、頭で考えるだけでなく、しっかり行動できるアピールが大切です。
仕事は言われたことをすぐに実行する人は多いですが、言われる前に自分で考えて行動できる人は少ないのですから。
入社意欲の高さは企業研究の量に比例する


役員は『熱意の量』をどうやって測っているのでしょうか?
「絶対に入社したい!」と、気持ちで思っても伝えるのはなかなか難しいですよね。面接官も熱意の量を外見だけで判断することはできません。
しかし、熱意の量を判断する指標があるのです。それは『企業研究の量』なのです。
熱意は企業研究の量に比例する
入社意欲や熱意の高い人は必ず企業をよく調べています。私の経験から『入社意欲の高さは企業研究の量に比例する』と考えています。
例えば、大好きはアニメ、マンガがあれば、作者は誰なのか、原作の本はあるのか、映画の計画はあるのかなど調べますよね。そうです、関心が高いほど調べる量や時間は長くなります。
逆に関心が薄ければ、最初に少し調べて終わりですよね。企業研究も同様に第1志望と第5志望では調べる量や時間は違いませんか?
よって役員や面接官は入社意欲の高さは企業研究の量で測っているのです。
そのため、最終面接に進めば、ホームページや他社との違いをもう一度復習しておきましょう。
企業研究の量を確認される質問
ではどういった質問で確認されるのでしょうか?
ホームページ、会社説明会で業務内容はしっかり把握できてますよね。
では同業他社の比較はしてますか?
例えば自動車メーカーを考えているのに、トヨタ、ホンダ、日産、スバル、マツダは絶対に調べますよね。
この質問で企業研究の量を測ることができるのです。
・他社と弊社の違いは何だと思いますか?
・同業他社ではなく、なぜ弊社を選んだのですか?
この2点を深堀した質問をすれば、あなたがどれだけ企業研究をしているかわかるのです。
- 売上規模
- 従業員数
- 拠点数
- 創業
- 経営理念
- 品質方針
- 主要取引先
- 一番の特徴
- 会社の強み弱み
- 伸ばしている分野
- 最新情報
各項目をノートにまとめて比較すると違いがわかります。詳しく答えることができれば、かなりの加点となります。
イメージだけで答えると、突っ込んだ質問がきた時に、答えられなくなります。
最終面接は最初の5分が勝負


役員は経験が豊富なので人を見る目は確かです。人事部が気づきにくい点を指摘したり、推察能力も長けています。
最終面接は30分~1時間がほとんどですが、最初の5分で合否を決めていると言っていいでしょう。
最初の挨拶もムダにできません。
・背筋を伸ばす
・まっすぐ目を見る
・ハキハキした挨拶をする
上手く話そうとせず、シンプルに回答する方が自分らしさを伝えられます。
大事なのは『自信なさそうにしない』ことです。目線を下げたり、質問に詰まって頭や耳を触ったりしないようにしましょう。
途中で会話尻つぼみしないよう、しっかり言い切ることがポイントです。語尾が聞こえにくいと特に自信がないように聞こえるからです。
役員は第一印象であなたの持っている雰囲気、話し方、表情そして熱意を経験則に基づいて瞬時に判断するのです。
※よって最終面接は最初の5分が勝負と思いましょう。
>>【採用者回答】面接は見た目で決まるって本当?意識することは【2つだけ】
人事部はバランスを考慮


とは言っても役員が全てを直感で決められては配置に偏りがでます。人事部は全体のバランスを考え合否について助言をします。
<人事部はバランスを考慮>
・男女比
・勤務地
・職種
・理系と文系
・学卒と院卒
例えば、男女の割合を考えたり、全国規模なら希望勤務地が偏らないようにしています。理系と文系の比率、4大卒と大学院卒の割合など全体のバランスをとっているのです。
そのため二次面接であらかじめバランスを考慮して合格を出しているのです。
最終面接で合否を役員と打ち合わせる際は必ず、男女比、希望職種、希望勤務地、営業と技術の割合などを助言します。
最終面接対策のまとめ
1.一次、二次面接と最終面接の合格基準の違い
・人事部から役員に決裁者が変わる
・能力重視から熱意重視に変わる
・絶対的から相対的評価に変わる
2.役員へは熱意をアピールすることが大事
・論理的ではなく、入社意欲、忠誠心をアピール
・チャレンジ精神をもち、行動力があることをアピール
3.最終面接は最初の5分が勝負
・第一印象、話し方、表情、雰囲気で瞬時に判断される
・語尾を意識して、言いきれば自信あるように聞こえる